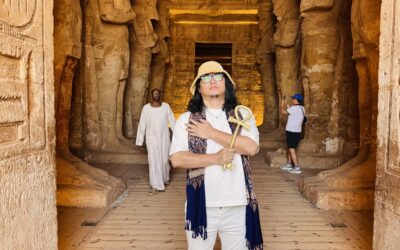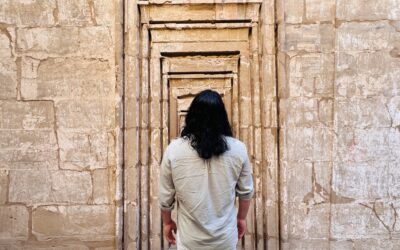自分がやりたいことをやらなかったら ──その人生は、一体誰のものになるのでしょうか。 多くの人は「生活のため」「家族のため」「会社のため」と言い訳を並べます。 確かに、それは責任感のある立派な姿に見えるかもしれません。 しかし、その責任を理由にして「自分の軸」まで手放してしまったら どうなるでしょうか。 朝、鏡を見ても疲れ切った顔が映るだけです。 電車の窓に映るのは、「誰かの期待に応えること」だけに追われる自分です。 気がつけば、一日の中で「本当に自分が望んだこと」に触れる時間が ゼロになっています。...
華僑Jビジネス日記
華僑Jの日々の気づき
【暇そうに見えるリーダー”ほど、会社を伸ばす】
現場から見れば、不思議に映るかもしれません。 会議に顔を出す回数も少なく、細かい業務に首を突っ込むこともなく、 「社長、最近何してるんですか?」──そんな声すら上がります。 けれど、そういうリーダーの会社ほど、不思議と現場はよく回ります。 数字がよく伸びるのです。 一方で、常にバタバタと忙しそうなリーダーもいます。 社員の前で「俺は毎日走り回ってる」と言い張り、 スケジュールをぎゅうぎゅうに詰め込み、 「忙しい=頑張ってる」という姿を見せようとします。 その姿は、最初は部下の目に“頼もしい”と映るかもしれません。...
【“顧客第一”の落とし穴】
経営者なら誰もが「お客様のために」という言葉を掲げます。 一見すれば立派な理念です。 しかし現実には、この思想を徹底するほど会社は弱っていきます。 理由は単純です。 顧客第一を優先する裏側で、必ず「従業員は二の次」に追いやられるからです。 無理な納期、過剰な要求への対応、休みを削る働き方。 従業員は疲弊し、やがてモチベーションを失っていきます。 その状態で顧客に本物の価値を届けられるでしょうか。 答えはノーです。 顧客を守るために従業員を犠牲にする会社は、最後には顧客すら失います。 一方で、持続的に成長している企業は違います。...
【感情が強い社長ほど、組織から事実が消える】
「社長が感情的になればなるほど、会社から“事実”が消えていきます。」 社員のミスや報告漏れ、取引先とのトラブル。経営者であれば誰でも、 つい感情をあらわにしたくなる瞬間があります。 しかし、その怒りをそのままぶつけた瞬間、組織の空気は変わります。 社員は「成果を出すこと」より「怒られないこと」を優先するようになります。 その結果、ミスは隠され、数字は加工され、 経営者が一番必要とする“本当の情報”は上がってこなくなります。 つまり、感情的な一言が積み重なるほど、会社から事実が静かに消えていくのです。...
【社長が働けば働くほど、会社は社長に依存する】
「社長が働けば働くほど、会社の寿命は縮まります。」 多くの経営者は「自分が誰よりも働けば会社は守れる」と信じています。 しかし、その考えこそが会社を弱らせていきます。 社長が働きすぎるほど、会社は社長に依存し、自分で考え、 動く力を失っていくのです。 もし社長が倒れれば、会社のすべてが停止します。 これは経営における“致命的なリスク構造”です。 どれほど業績が伸びていても、その基盤が「社長一人の頑張り」に乗っている時点で、 会社の未来は極めて脆弱です。 本当の経営とは、社長が働かなくても会社が回る仕組みを設計することにあります。...
【人が辞める組織】
人が辞める組織とは何でしょうか。 「“この社員は絶対に辞めない”──実はそう思った瞬間が、一番危険です。」 経営者は安心したいのです。 「こいつだけは辞めないだろう」と信じたいのです。 しかし現実は逆で、そういう社員ほど突然辞表を置いて去っていきます。 なぜでしょうか。 それは、経営者が“成長欲求”を過小評価しているからです。 社員は待遇だけで残るのではありません。 給与や制度は安心を与えますが、未来を与えることはできません。 本当に優秀な社員ほど、「ここに居続けることで、自分はどれだけ成長できるか」を 常に測っています。...
【利益を追うほど、利益は逃げる】
「利益だけを追う会社は、必ず利益に蝕まれます。」 多くの経営者は「利益を出すことこそ会社の使命」だと信じています。 しかし、その思考こそが会社を静かに壊していきます。 なぜでしょうか。 利益ばかりに目を奪われた瞬間に、利益を生む本質である顧客の幸福や社員の 成長から目を逸らしてしまうからです。 利益は数字でも記号でもありません。 利益の正体は「人が感じる価値」であり、 「人が得る幸福」にほかなりません。 そこを忘れた会社は、次第に空虚な“利益追求マシーン”と化します。 顧客の声も、社員の未来も聞かず、...
【愛情を注ぐかすぐ切るか】
社員をすぐ切る経営者と、愛情を注ぎ続ける経営者。 どちらが正しいのか。 実は、この二択の議論自体が、本質を外しています。 まず理解すべきは、経営者には「幸せにできる人」と「幸せにできない人」が いるという事実です。 どれだけ面倒を見ても、時間やお金を投じても、経営者が用意できる環境と 社員の望む未来がかみ合わないことはあります。 このズレは、努力や愛情では埋まりません。 「すぐ切る経営者」は、このズレを早く見抜き、 組織の未来を守るために決断します。 冷たく映りますが、本人にとっても早く次の環境に進めるという意味では、...
【正論では、人は動かない】
部下が動かないのは、怠けているからではありません。 あなたの正論が“理由”を奪っているからです。 多くの上司は部下にこう言います。 「これをやった方がいい」「こうするのが正しい」 しかし人は、正しいから動くわけではありません。 人が動くのは、その行動に“自分の理由”を見つけたときです。 命令や押し付けは「やらされ感」を生みます。 逆に「やりたい理由」を引き出す言葉は、人を自発的に動かします。 「あなたならできると思った」 「これが実現すれば、あなたの目標にも近づく」 「ここは、あなたの強みが活きる」...
【意味のない会議を続ける会社は、必ず未来を失う】
──これは誇張ではありません。今この瞬間にも、組織は静かに腐敗しています。 結論も出ず、行動計画もなく、ただ時間を消費するだけの会議。 その裏で社員の集中は削がれ、やる気は奪われ、会社の血は流れ続けています。 人件費に換算すれば、一度の無駄な会議で数十万円です。 年間に直せば、未来の投資資金を丸ごと燃やしているのと同じです。 無意味な会議には、決まって共通点があります。 ・目的が曖昧なまま集まります。 ・資料や情報が事前に共有されていません。 ・誰が何を決めるのか不明確です。 ・発言が一部の人間に偏ります。...
【「優秀そう」は“毒”?】
「“優秀そうに見える人材”を採った瞬間、会社は静かに壊れ始めます。」 これが採用に潜む、最も恐ろしい現実です。 履歴書は完璧で、面接の受け答えもスマートで、そしてスキルも申し分ありません。 経営者や人事から見ても「即戦力だ」「間違いなく優秀だ」と太鼓判を押したくなります。 しかし入社して数ヶ月が経つと、その仮面の裏に潜む“有害な社員”の本性が姿を現します。 表向きは成果を出しているように見えても、 仲間のモチベーションを削ぎ、信頼を侵食し、組織を内部から腐らせていきます。 経営を崩すのは無能ではありません。“優秀に見える毒”です。...
【厳しさで回る組織ほど、静かに崩れる】
実は厳しくないリーダーほど、現場をうまく回しています。 「“厳しいリーダーが現場を締める”」 そう信じているなら、あなたの組織はもう静かに崩壊を始めています。 実は、最も成果を出している現場には、怒鳴り声も威圧感も存在しません。 そこにあるのは、厳しさではなく、透明な秩序です。 多くの経営者は誤解しています。 「厳しく接すれば、部下は緊張感を持って動く」と。 しかし現実は逆です。 叱責や恐怖で動く社員は、一見従っているように見えても、 内心では「どうすれば怒られないか」だけを考えています。 そこに主体性も創造性もありません。...