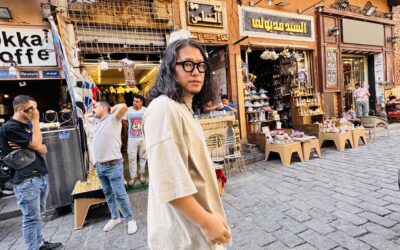私がずっと違和感を持っているのは、 多くの人が「足りないもの」から自分を作ろうとすることなんです。 できなかったこと、弱いところ、まだ足りない知識。 もちろん改善は必要なんだけど、そこを起点にすると、 人生もビジネスも一気に重たくなるんですよ。 本当は逆なんです。先に見るべきは「できていること」。 すでにやれていること。無意識にやってしまうこと。 それは弱点じゃなくて、強みなんですよ。 しかも強みは、磨けば磨くほど伸びる。 弱みは埋めても平均に戻るだけだけど、強みは突き抜ける可能性を持っている。 ここで一つ、大きなズレが起きます。...
華僑Jビジネス日記
華僑Jの日々の気づき
【管理職はなぜ「罰ゲーム」?】
管理職がなぜ罰ゲームに感じるのか。 それは、あなたが“人で管理”してるからです。 部下を監視して、叱って、押しつけて。 ――そのやり方を続ける限り、管理職は永遠に地獄なんですよ。 管理職が罰ゲームに見えるのは、 「自分でやる」「人に任せる」「文化で動かす」―― この3つの役割を切り替えられていないからです。 成果も出せず、人も動かせない。 その板挟みが、管理職を一番苦しめるんです。 だから、結果は出してるのに、気づけば誰もついてこない。 部下は「この人は優秀だけど、自分と同じやり方は無理だ」と感じて距離を取る。...
【実行力のない部下の変え方】
『うちの部下は実行力がない』 そう言うリーダーほど、実は誤解していることがあるんです。 会議ではうなずくのに、現場では何も進まない。 「昨日の件はどうなった?」と聞いても、報告は上がってこない。 その姿を見て「やる気が足りない」「能力が低い」と愚痴をこぼしていませんか? でも原因は──部下の資質ではなくて 背景には、もっと構造的な理由があるんです。 部下が動けない理由は、大きく五つに整理できます。 研修制度が整っていないから、新人は同じミスを繰り返す。 権限と役割が曖昧だから、「これをやっていいのかな」と立ち止まる。...
【最初を制す者が勝つ】
「新しい管理職に就いた瞬間、あなたは“試される舞台”に放り込まれます。 最初の立ち上がりを誤れば、『口だけの人間』と烙印を押されます。 逆に最初で掴めば、半年後の評価は激変します。」 部下は肩書きに従いません。 彼らが見ているのは、言葉ではなく“あなたの姿勢”です。 一流の管理職はまず、現場で一番キツい場所に飛び込みます。 泥臭くても構いません。小さな成果でもいいです。 自ら矢面に立ち、「この人は現場を理解している」と思わせます。 その一手で信頼の基礎は築かれます。 次に、一番扱いにくい人間と向き合います。...
【成果の差は〇〇の差】
「結果を出す人間は“努力量”が違う──そう思っているなら、それは幻想です。 本質は、やることの多さではありません。 実は“選ぶ精度”の差なんです。」 凡人ほど、選択肢を並列に積み上げます。 「これもやっておいた方がいい」 「あれも一応押さえておこう」 「みんながやってるから自分も」 一見、前向きに見えますが、そこに基準がなければ浅く広がり、 結局は疲弊して終わります。 結果を出す人は真逆です。 「この土俵なら勝てる」 「この方法が未来に直結する」 「この一点に全てを賭ける」 彼らは“やること”ではなく、“捨てること”を徹底します。...
【優しさと甘さの境界線】
「優しさで部下が動くと思っている経営者が気づいていないことがあります。 それは“優しさ”と“甘さ”の区別です。」 甘やかせば、人は堕落します。 基準を示さなければ、人は迷います。 決定権を奪えば、人は思考を捨てます。 その結果、 「社員が受け身なんです」「主体性がないんです」と愚痴をこぼします。 社員が腐ったのではありません。 腐らせたのは経営者自身です。 無知な勤勉ほど危険なものはありません。 “頑張ってる風”の社長ほど、会社を最速で壊します。 方向音痴のランナーが全力で逆走しているのと同じです。...
【組織に居座る“害獣”】
「チームを壊すのは無能な人間ではありません。 本当に危険なのは、組織に居座る“害獣”です。」 それは、野良犬・狐・狼・マムシ・うさぎです。 見た目は一見普通の社員でも、その振る舞いは確実に組織を蝕んでいきます。 ① 野良犬 他人の資源は奪うのに、自分のものは絶対に譲りません。 自分のためなら平気で仲間を踏み台にし、短期的な利益しか眼中にありません。 こういう人間がいると、組織の信頼関係は一瞬で崩れます。 ② 狐 ずる賢く、口はうまいですが手は動きません。 常にグレーゾーンに身を置き、責任を回避します。...
【目先の得は未来を奪う】
「今日の利益にすがる人間は、明日の利益を捨てています。 そしてその姿勢を続ける限り、一生成功の入り口には立てません。」 多くの人は“今すぐの得”に飛びつきます。 残業代を稼ぐために無意味な時間を積み重ねます。 楽だからと、成長のない仕事に安住します。 欲望に任せて浪費し、一瞬の快楽を買います。 その場では満たされるかもしれません。 しかし気づかぬうちに、“未来の可能性”を切り売りしているのです。 本当に成功する人は、“明日の利益”を優先します。 今日の報酬ではなく、未来の資産を育てることに意識を向けます。 勉強に時間を投資します。...
【沈黙で生まれる差】
「一流は結果で語ります。 二流は言葉で飾ります。 その差が、やがて埋められない格差となります。」 批判されたときに正体が出ます。 一流は黙って耐え、結果で黙らせます。 二流は弁解を並べ、言葉に逃げます。 声を荒げた瞬間に、勝負はもう決まっています。 一流は孤独を恐れません。 理解されなくても、最後に成果が全てをひっくり返すと知っているからです。 二流は孤独を避け、仲間を集めて傷を舐め合います。 しかし安心感は一瞬で消え、残るのは時間の浪費だけです。 ――ここで重要なのは、凡人が二流からどう抜け出すかです。...
【賢い人の怒りの“使い方”】
「賢い人ほど“ムカつきません”。 それは、怒りを感情だと思っていないからです。 賢い人は、怒りはコントロール不能な爆発ではなく、 目的を持って解き放つ“道具”だと知っています。」 未熟な人間ほど、思い通りにならないと声を荒げます。 相手を威圧すれば強さを示せると思い込みます。 しかし現実は逆です。 感情に飲み込まれた瞬間、自分を制御できていないことをさらしています。 怒鳴ることは強さの証明ではなく、無力の告白です。 本当に賢い人は違います。 怒るときは“理由”があります。...
【動かないのは社員のせい?】
「社員が動かない理由を“社員の怠慢”にすり替える経営者は、 自らの無能を隠しているにすぎません。」 人間は本来、自ら動きたがる生き物です。 子どもですら、やらされる宿題には反発し、 自分で選んだ遊びには命をかけるほど全力を注ぎます。 それなのに社員だけが“受け身”になるのはなぜでしょうか。 原因は社員ではなく、環境をつくる側にあります。 主体性を奪う最大の毒は、経営者自身の姿勢です。 細かい指示に従わせ、ルールで縛り、決定権を握り潰します。 その瞬間に、社員は考えることをやめます。...
【救える社員と救えない社員】
「炎上するかもしれませんが、 はっきり言って“静かな退職”している人は、会社にとって深刻な問題です。 みんな言いにくいから代弁しますが、 会社にぶら下がっているだけの人間は、必要ありません。」 大企業なら、そんな社員も余剰人員として抱え込むことができるかもしれません。 しかし、中小企業にはそんな余裕は一切ありません。 一人の無気力が、全員の足を引っ張り、チームの空気を濁らせ、 組織全体を弱らせるからです。 経営者が本当に恐れるべきは「スキルが足りない社員」ではありません。 スキル不足は教えれば伸びます。...