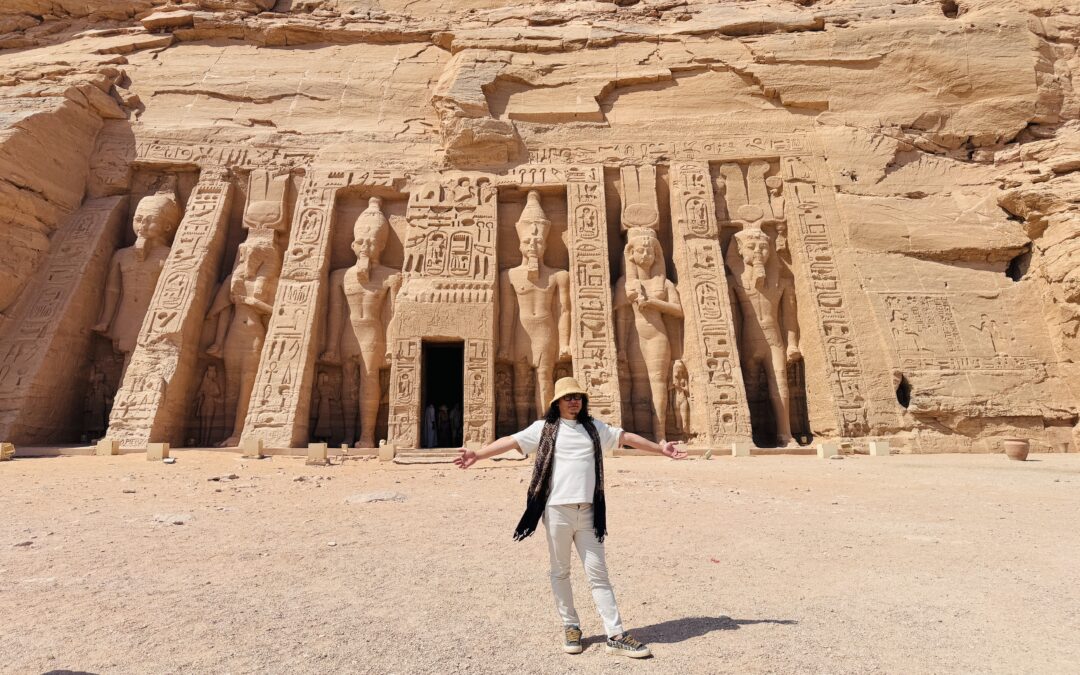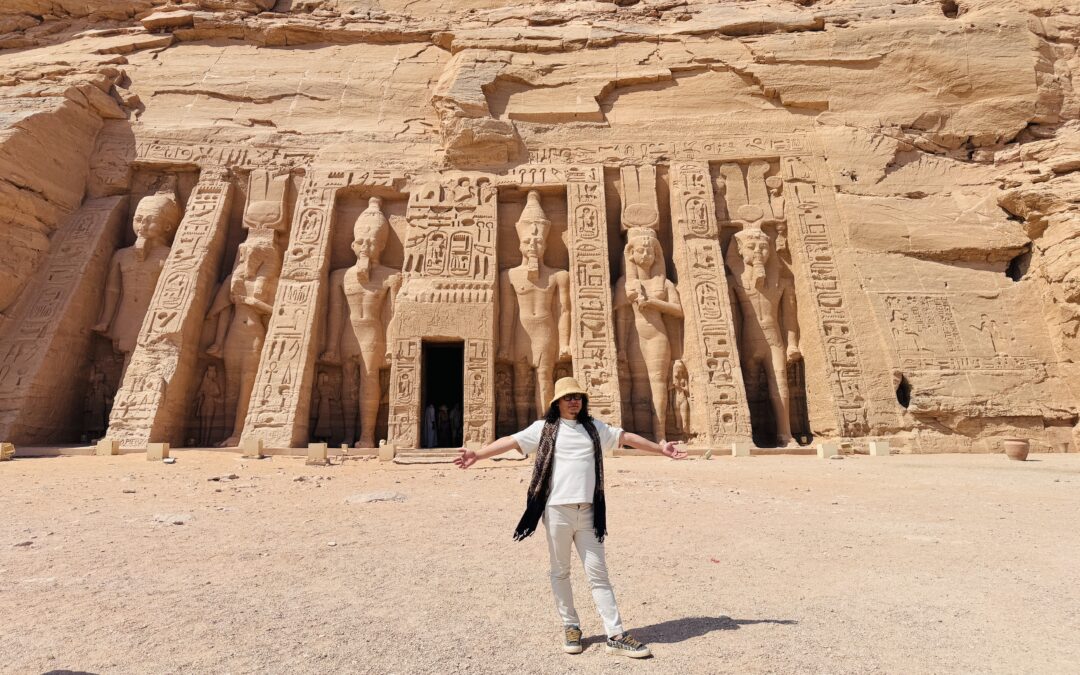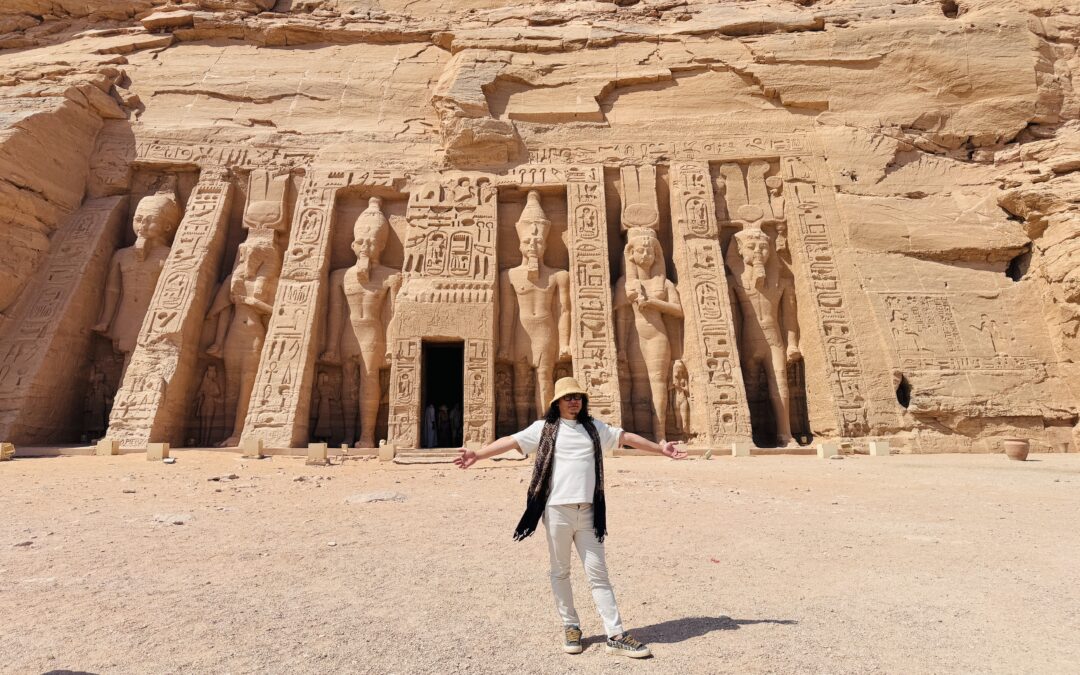
執筆者 華僑J | 1月 17, 2026 | ビジネス日記
“負ける奴には、意外なほど共通点があります。” 彼らは才能がないわけでも、努力を怠っているわけでもありません。 むしろ人一倍真面目に動いています。 しかし最後には、同じように敗北していきます。 なぜでしょうか。 それは「考えること」より「動くこと」で安心してしまうからです。 忙しさに酔い、汗を流した自分に酔い、「これだけやった」と自分を慰めます。 しかしその姿は、銃弾が飛び交う戦場で剣を振り回す兵士と同じです。 戦っているように見えて、実際には“自ら負けに行っている”に過ぎません。 もう一つの共通点は、視点の短さにあります。...

執筆者 華僑J | 1月 16, 2026 | ビジネス日記
自分がやりたいことをやらなかったら ──その人生は、一体誰のものになるのでしょうか。 多くの人は「生活のため」「家族のため」「会社のため」と言い訳を並べます。 確かに、それは責任感のある立派な姿に見えるかもしれません。 しかし、その責任を理由にして「自分の軸」まで手放してしまったら どうなるでしょうか。 朝、鏡を見ても疲れ切った顔が映るだけです。 電車の窓に映るのは、「誰かの期待に応えること」だけに追われる自分です。 気がつけば、一日の中で「本当に自分が望んだこと」に触れる時間が ゼロになっています。...

執筆者 華僑J | 1月 15, 2026 | ビジネス日記
現場から見れば、不思議に映るかもしれません。 会議に顔を出す回数も少なく、細かい業務に首を突っ込むこともなく、 「社長、最近何してるんですか?」──そんな声すら上がります。 けれど、そういうリーダーの会社ほど、不思議と現場はよく回ります。 数字がよく伸びるのです。 一方で、常にバタバタと忙しそうなリーダーもいます。 社員の前で「俺は毎日走り回ってる」と言い張り、 スケジュールをぎゅうぎゅうに詰め込み、 「忙しい=頑張ってる」という姿を見せようとします。 その姿は、最初は部下の目に“頼もしい”と映るかもしれません。...

執筆者 華僑J | 1月 14, 2026 | ビジネス日記
経営者なら誰もが「お客様のために」という言葉を掲げます。 一見すれば立派な理念です。 しかし現実には、この思想を徹底するほど会社は弱っていきます。 理由は単純です。 顧客第一を優先する裏側で、必ず「従業員は二の次」に追いやられるからです。 無理な納期、過剰な要求への対応、休みを削る働き方。 従業員は疲弊し、やがてモチベーションを失っていきます。 その状態で顧客に本物の価値を届けられるでしょうか。 答えはノーです。 顧客を守るために従業員を犠牲にする会社は、最後には顧客すら失います。 一方で、持続的に成長している企業は違います。...

執筆者 華僑J | 1月 13, 2026 | ビジネス日記
「社長が感情的になればなるほど、会社から“事実”が消えていきます。」 社員のミスや報告漏れ、取引先とのトラブル。経営者であれば誰でも、 つい感情をあらわにしたくなる瞬間があります。 しかし、その怒りをそのままぶつけた瞬間、組織の空気は変わります。 社員は「成果を出すこと」より「怒られないこと」を優先するようになります。 その結果、ミスは隠され、数字は加工され、 経営者が一番必要とする“本当の情報”は上がってこなくなります。 つまり、感情的な一言が積み重なるほど、会社から事実が静かに消えていくのです。...

執筆者 華僑J | 1月 12, 2026 | ビジネス日記
「社長が働けば働くほど、会社の寿命は縮まります。」 多くの経営者は「自分が誰よりも働けば会社は守れる」と信じています。 しかし、その考えこそが会社を弱らせていきます。 社長が働きすぎるほど、会社は社長に依存し、自分で考え、 動く力を失っていくのです。 もし社長が倒れれば、会社のすべてが停止します。 これは経営における“致命的なリスク構造”です。 どれほど業績が伸びていても、その基盤が「社長一人の頑張り」に乗っている時点で、 会社の未来は極めて脆弱です。 本当の経営とは、社長が働かなくても会社が回る仕組みを設計することにあります。...